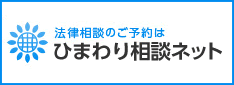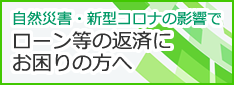会長声明・決議
会長声明・決議
今次の少年法改正案に反対する会長声明
2021(令和3)年2月19日、内閣は、「成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み、年齢満十八歳以上二十歳未満の特定少年に係る保護事件について、(改正案に規定する特例)措置を講ずる必要がある」との理由で、「少年法等の一部を改正する法律案」を通常国会に提出した。その内容は、法務省の諮問機関である法制審議会が2020(令和2)年10月29日に採択した答申に従ったものである。
法案が、罪を犯した満18歳以上20歳未満の者に係る事件をこれまで通り少年法の適用対象とし、全件を家庭裁判所に送致して保護事件として取扱う枠組みを維持している点は、20歳未満の者が「類型的に」「未だ十分に成熟しておらず、成長発達途上にあって可塑性を有する存在である」こと(上記答申より)、そして、現行少年法下での18歳及び19歳の少年に対する手続きや保護処分が有効に機能してきたことの正当な認識に基づくものとして評価できる。
しかし、法案が規定する特例措置は、その認識とは真逆の意図に出たものであり、「類型的」に未熟な満18歳以上20歳未満の少年が、保護処分による教育的な処遇によって立ち直る機会を大幅に制約する内容となっており看過できない。
すなわち、法案は、まず、満18歳以上20歳未満の者を「特定少年」と位置づけ、特定少年については、①犯罪には当たらないとの理由で「ぐ犯」を適用対象から除外し、また、②保護処分の内容も、「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内」において一定の処分しか出来ないものとしている。
しかし、この改正は、現行の実務が「ぐ犯」を理由に少年の非行に介入し、福祉的・教育的観点から保護処分を選択することにより、最後のセーフティネットとしての機能を果たしてきた実情を見過ごすものであり相当でない。例えば、家出をして性風俗業に関係している女子少年に、反社会的集団に引き込まれて犯罪に及ぶ等といった惧れが認められる場合、実務は「ぐ犯」を理由に介入し、保護観察処分や少年院送致を選択してきた。また、犯罪による被害結果が軽微な場合でも、家庭裁判所の調査の結果、積極的な介入が必要であることが判明した場合には、成人であれば執行猶予付判決で社会復帰できる事案でも、施設収容等の処分で臨むことも辞さず、教育的な働きかけにより更生へと導いてきた。法案は、特定少年について実務が果たしてきたこれら福祉的・教育的な機能を奪う内容となっていることから、強く反対する。
更に、法案は、特定少年については、③原則的に家庭裁判所から検察官に送致して刑事事件として扱わなければならないとする対象事件(いわゆる原則逆送対象事件)の範囲を、従来の「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」から、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件」にまで拡大し、しかも、④検察官により起訴された場合は、「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知できるような記事又は写真」の掲載禁止(いわゆる推知報道の禁止)の規定の適用を廃除するとした。
短期1年以上の犯罪には強盗罪があるが、これには例えば、万引き現場を見つかり制止を振り切ろうと軽微な暴行に及ぶといった事案も含まれる。また、犯行に至る経緯、動機、態様及び結果等は様々である。それにも拘わらず、文字通り一律「原則」逆送されることになれば、特定少年のこれらの犯罪については、諸事情を考慮した上で対象者の立ち直りに向けた処分をきめ細かく行うための家庭裁判所の調査や審理は形がい化を免れない。少年の要保護性の高い事案が、刑事裁判においていとも簡単に執行猶予となり、少年の立ち直りや再犯防止の観点から逆効果となる事態もありうる。現行法においても、家庭裁判所の調査の結果、刑事処分相当と認められれば逆送されるのであり、改正の必要は乏しい。
また、推知報道が解禁されれば、インターネットの普及した現代社会においては、特定少年の立ち直りの機会を大きく制約することは想像に難くない。
勿論、提案理由にあるとおり、これらの特例措置が「成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化及び少年による犯罪の実情に鑑み」て真に必要な措置となっているのであれば、従来の実務を改めることも一つの見識ではある。
しかしながら、ここでいう「成年年齢の引下げ等の社会情勢の変化」とは、18歳及び19歳の者は、選挙権及び憲法改正の国民投票権を付与され、民法上も成年と位置付けられるに至ったことを指すものと解されるところ、各法律の適用年齢はその法律の目的ごとに定められるべきものである。現に、未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法、競馬法は、彼らの健康やギャンブルの依存性に鑑みて、従来通り20歳まで飲酒・喫煙・馬券の購入を禁止する立場を維持している。18歳未満の者同様「類型的」に未成熟な彼らに対して少年法による教育的な処遇を行う必要性は高く、殊更に18歳未満の者と別異に取り扱う特例を設けるべき理由は無い。
また、「少年による犯罪の実情」とは、巷間言われる少年犯罪の激増及び凶悪化、質的変化を指すものと解される。しかし、法務省作成の犯罪白書の統計が示すとおり、児童人口の減少を勘案しても少年犯罪の認知件数は大幅に減少し、平成24年以降は戦後最少を記録し続けているのが現状である。また、凶悪犯罪も減少し、過去の事例との比較において、少年犯罪に凶悪化も質的変化も認められない。つまり、法案の立法事実は認められないのであり、これまでの実務を改める理由とはならない。
以上の理由から、当会は、今次の少年法改正案に強く反対する。
2021(令和3)年3月9日
滋賀弁護士会
会 長 西 川 真美子